18世紀から20世紀前半の西洋音楽界の大きな流れには「拡大」という傾向が見られます。例えば、鍵盤楽器の音量の拡大。ピアノが開発されるまで主流だった鍵盤楽器、チェンバロ(ハープシコード、クラヴサン)の弦を弾く部分には鳥の羽の軸となっている部分が使用され、その音量は今のピアノとは比べ物にならないほど小さなものだったそうです。それがもっと大きな音量の出るピアノにとって変わられ、その後ピアノはどんどん大きな音が出るように改良が加えられていきました――ここには宮廷や屋敷といったパーソナルな空間で演奏される用の楽器が、コンサートホールというさらに大きな空間(市民的な公共空間)での演奏用に改造されるという「時代の要求」が読み取れます。
拡大したのは音量だけではありません。オーケストラの規模も拡大していきます。奏者の数はベートーヴェンの時代からマーラーまでで倍以上になり、また仕様される楽器も増えていきました。驚かれることかもしれませんが、今ではとてもポピュラーな木管楽器であるクラリネットもオーケストラで使われ始めたのはモーツァルトの時代に入ってからです。どのような楽器が使用されるか、という事柄に関しては19世紀に入って大体決まってしまうのですが、そこで変化を止めないのが近代人の性。中には「こんな楽器を作って欲しい」と楽器製作者に開発させた人もいました。
世界に存在する珍楽器愛好家の皆様、こんにちは。申し遅れましたが私、mkと申します。世界のどこにも存在しない妄想の博物館、珍楽器妄想博物館の館長を務めております。今回はそのような時代の変遷のなかでオーケストラのなかに加えられた珍しい楽器に焦点を当て、皆様の知的好奇心をくすぐっていこうと思います。
作曲家の要求によって開発された楽器の代表格と言えばこの「ワーグナー・チューバ」。名前の通り、リヒャルト・ワーグナーによって開発された金管楽器です。チューバと言えども、担当するのはホルン奏者(演奏中に持ち替える)。使用していたのはワーグナーだけではなく、むしろワーグナーの熱狂的信奉者であったブルックナーの方が使用していた作曲家として有名かもしれません。
映像はブルックナーの交響曲第7番(演奏はクラウディオ・アバド/ルツェルン祝祭管弦楽団)。2:45あたりから荘厳な響きを聴かせてくれますが、これは結構「玄人好みするタイプ」の音色であろうと思います。生、あるいは映像で見ないと「これがワーグナー・チューバの音色だ」と認識できる日は来ない……折角開発されたのにそういう悲しい運命を背負った楽器であるとも言えます。ちなみに、これ以降も取り立ててこの楽器がメジャーに取り扱われることはなく「特殊楽器」として認知されています。日本のアマチュア・オーケストラでは早稲田大学のオケが所有しており、他の団体がブルックナーなどを演奏する際に貸し出しが行われていたりするそう。「ワグチュー」と略して呼べば途端にあなたも玄人扱いされること請け合い。
こちらの「ヘッケルフォン」も作曲家の要請によって開発された楽器です。これはリヒャルト・シュトラウスが現在も世界最高峰のファゴットを製造し続ける楽器工房「ヘッケル」に頼んで作らせた「ファゴットよりは小さく、イングリッシュ・ホルンよりは大きい」木管楽器。リヒャルト・シュトラウス以外に使用した人を私は知りませんが、現在でも製作されており日本の楽器屋さんでも普通に買えます(たぶん乗用車が新車で一台買えるぐらいの値段)。買っても何に使えば良いのか知りません。あとどんな音がするか、私もよくわかりません。
ヘッケルフォンはこちらのサイトに詳細があります。リヒャルト・シュトラウス以外にもパウル・ヒンデミットがヘッケルフォンのための作品を書いているそうです。オーケストラで使用するほとんどの楽器のためにソナタ作品を書いたといわれるヒンデミットですが、ここまで来るともう意地としか思えません。
珍しい楽器を使用したことではリヒャルト・シュトラウスと同時代の作曲家、グスタフ・マーラーも負けてはいません。こちらの動画は交響曲第6番第4楽章で使用される打楽器「ハンマー」。「もはや何でもありだな!」という感じがしますが、これを生で見れた幸運な方はやはり痺れてしまうでしょう。音自体はそこまで衝撃的ではありませんが、見た目のインパクトがすごすぎます。マーラーは他にも交響曲第7番でリュートやカウベルを使用しています。このカウベルも舞台裏であんまりオーケストラと関係なく鳴らされてるのでびっくりする。ちなみにリヒャルト・シュトラウスもカウベルを《アルプス交響曲》で使用しています。この曲は他にもウィンドマシン(風の音が出る)やサンダーマシン(雷の音が出る)など珍しいものがある。
《アルプス交響曲》で使用されている珍楽器はこちらでもまとめて紹介されています(ヘッケルフォンの音が聴けるサイトへのリンクも貼られている)。よく見たらこれ、知り合いが参加してるオケのサイトじゃないか……。
今回はオットリーノ・レスピーギの交響詩《ローマの松》より「ジャニコロの松」でお別れ(演奏はアルトゥーロ・トスカニーニ/NBC交響楽団。この曲ではラストで「鳥の鳴き声が収録されたレコード」が用いられています)。当博物館では、皆様のまたのご来場を心待ちにしております。
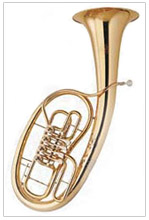


館長様
返信削除次はコダーイあたりでぜひ。
当博物館は楽器を主な展示物としておりますので、作曲家の企画展はおこなう予定はありません。ご了承ください。コダーイですと「変則チューニング」が思い浮かびますが、どのように取り扱って良いか悩みます。
返信削除館長。
返信削除コダーイといえば、ツィンバロム(ハンガリー語でCimbalom)でいかがですかという提案でございます。
「ハーリ・ヤーノシュ」です。
勉強になりました。実はあまりコダーイに明るくないのです。この作曲家といえば、私の地元にコダーイの名前を冠した合唱団がありましてCDデビューまでしていたことが思い出されます。
返信削除